第一日(平成18年7月8日)
全国学剣連の講習会は,全剣連,学剣連からそれぞれ3名,計6名の講師をお迎えして広島サンプラザを会場に開催されました。
開講式では,本部役員小久保昇司先生の「講師の先生方も,われわれ学剣連の仲間です」という言葉に緊張がほどける思いがしました。
最初の講話は,脇本三千雄先生による「諸学校の教育目標と剣道」でありました。これがなんと,資料は学習指導要領であります。さすがは「全日本学校剣道連盟」。そういえば,我が母校M町高校では,「武道場」ではなく「格技場」と呼んでおりましたが,これも「格技」が「昭和33年以降,主として学習指導要領上一つの運動領域の名称として用いられてきた」からだとわかり,事務局長深く納得。「格技」から「武道」へと名称が改められたのは,平成元年版の指導要領からということで,これは結構新しいですね。この講話では,保健体育科で剣道をどのように扱うかを中心に話されました。小,中,高の保健体育科の目標ではいずれも「心と体を一体としてとらえ」が強調されておりました。また,中学校体育の目標の中には,「競争や協同の経験」がありました。そして武道のねらいとして「相手の動きに対応した攻防ができるようにする」が上げられており,さらに剣道で重視される態度として「礼儀作法や相手を尊重する態度」が最初にありました。「そーか,そーだったのか!」と深く納得する事務局長でありました。しかし,しかしであります,今回受講生の多くは保健体育科の教員(40名)でありますが,2番目に多いのが,なんと我が数学科(9名)でありました。従って,次回は「数学科における剣道指導について」でお願いしたいものであります。(というのは冗談です)
次の講話は福本修二先生の「諸学校の特性と剣道指導法」であります。いつもいつも聞かせていただいております。聴かせる講師としては岡村忠典先生と双璧を成すと,事務局長勝手に思っております。さて,戦前の「知識伝導型教育」から,戦後「問題解決型教育」に変わり,ほめて伸ばす指導法(教育)になった。しかし,中心にあるべき基本的なことが教えられていないという課題がある。ドーナッツ型学習になっている穴を埋めなければならないということを最初に言われました。しかし,なんと申しますか,関西弁でしゃべる人がみんなを漫才師に見えてしまうように,先生の「べらんめぇ調」は,なぜか上質の落語を聴くように心地よく耳に入ってくると感じるのは私だけでありましょうか。その後は「テキストに書いてあるこたー,よみゃーわかる」と無視(失礼!)され,福本ワールドに入っていきました。以下,私のつたない文章力では十分にお伝えできませんので,メモしたことをキーワードとして書かせていただきます。
・「自分で考え 自分で判断し 自分で実行し その責任(結果)は自分にある」
・「独立自尊の人」(福沢諭吉)
・理を知る 機を智る
・教師は名優たれ(子どもになりきらせる)
・メンタルトレーニング①個人差に応じた指導②言語による教育③視覚による師範④スキルに応じた指導⑤運動感覚的指導
その後昼食となり,午後からは村上済先生による「木刀による剣道基本技稽古法」であります。これは剣道社会体育指導員養成講習会(中級)の試験で一生懸命覚えたことがあり,思い出しながらやることができました。角正武先生は「諸学校における剣道技術指導法実習」として「木刀による剣道基本技稽古法」をもとに応用・発展させながら様々な技の稽古法をご指導下さいました。
休憩の後,先生方との稽古であります。私は福本先生に稽古をお願いしました。暑さのためにボーっとしていたため,あまりよく思い出せませんが,はっきりいえることは竹刀を飛ばされてしまいました。あー,ショック,はずかし。
全体での夕食をはさんで,20時からは「テーマ別研修会」があり,私はB班「部活動指導上の課題」に参加させていただきました。脇本,村上,藤原先生が指導・助言をされ,司会は地元宮本先生が務められました。とてもためになるお話ばかりでありました。私の部活動指導上の課題は,うーん,そうですねー,やはり・・・,「どうしたらうまく玉出しができるか」ですね(事務局長@卓球部顧問)。ちゃんちゃん。
その後都会の先輩や5月の八段審査で1次合格されたH多先生らと6人で串焼きを食べに繰り出す。軽く食ったつもりが,今年から県中体連専門委員長に就任されたI井先生から「よく食べますねー」と,次の日に言われてしまう。意外だ。
実り多い一日でありましたが,特に印象残ったことを一つだけ。講師を務められた草間益良夫先生は,全ての実習をビデオに撮り,また熱心にメモを取っておられました。とても蒸し暑い二日間だったのですが,終始姿勢を正して見学しておいででした。その姿にこそ学ぶべきものがあると直観した次第であります。
(文責はすべて事務局長にあります)
第二日(平成18年7月9日)
この講習会は,合宿による全日程(一泊二日)の受講が条件とされています。私は,同学年のH田先生と同室でした。高校時代には当時藤原先生が監督を務めておられたA芸高校へ出稽古に行き,H田先生と稽古したことを覚えております。さらに遡れば,来女木剣道スポーツ少年団が県下少年剣道錬成大会(現在のTSS杯)で準優勝した次の年,3年生のときに対戦したのが,H田先生の所属するS道館でありました。昨年の岡山国体では,少年女子の監督として見事に全国3位入賞を果たされ(コーチはmini98さんでしたね),実力・実績ともに我々の年代を代表する剣士であります。今回の講習会では,短い間ではありましたがなつかしく昔話ができたことをうれしく思いました。
さて,講習会は2日目に入りました。えーっと,なんかものたらんよーな気がする。なんじゃろう。うーん,おかしいなー。おおっ,そうじゃそうじゃ,朝稽古じゃ!!というわけで,まわりの人たちに「朝稽古は何時から?誰に掛かっていくん?」と1日目の夜に聞いてまわっていた事務局長でありますが,皆さんから「聞いとらんでー」とつれないお返事。そうなんです,今回の講習会では朝稽古はありませんでした。朝稽古,とっても大変なのに,無いと聞くと何かもの足らないとは勝手なものであります。
さて二日目は脇本先生,藤原先生による「日本剣道形及び指導法実習」から始まりました。脇本先生の歯切れ良い解説で,剣道形が少し上達したように感じました。
休憩をはさんで,午前中の最後は村上先生による「審判実習及び指導法実習」であります。村上先生からは昨年の正月に,都会の先輩,mini98さん,M実高校のN島先生と4人で広島から参加した勝浦の研修会でも審判法の指導をしていただいており,その時のことと重ね合わせながら聞くことができました。「剣道の審判が良くなれば剣道の試合が良くなる,剣道の試合が良くなれば剣道そのものが良くなる」とは,講義の中で何度も村上先生が言われたことでありますが,正にその通りであると実感する次第であります。
昼食をはさんで午後からは福本先生ほか全講師による「審判実習及び指導法実習」でありました。えー,わたくしこれまで数々の研修会やら講習会に参加してまいりました。今回の講師の先生方も,以前どこかでご指導いただいた方がほとんどであります。したがって,日程表をチラッと見ただけで「あっ,あれね」と,おおよその内容は予想はできるはずでありました。しかし,しかしであります。ここで衝撃的な事実が明らかになろうとは,まったく予想だにしないことでありました(って,ちょっとオーバーですね)。簡単に言うと,これまでに経験したことのない指導法実習を経験しました(こっちの方が早い)。ふつう審判法の講習では,「審判」→「試合」→「計時係」→「たすき係」→・・・,などいろいろな役割分担がありますが,今回は「指導係」(!?)なるものがありました。さすがは「全日本学校剣道連盟指導者講習会」であります。つまり,普段は講師の先生方が行っている審判員への指導や,さらには試合者に対する技術指導までをもこの「指導係」がやってしまおうというのであります。というのも「指導係」のみが教員で,あとはみーんな生徒という場面設定で行うため,当然「指導係」もそのように振る舞うことが要求されました。年長者や高段者に向けて「○○君,これはこーで,あれはあーだよっ!!」てなこともあり,緊張の中にもなぜかほのぼのとした雰囲気でありました。もちろんその背後には,講師の先生方の厳しい目が光っておりまして,ビシビシ指導を受けたことは言うまでもありません。
そして最後は「剣道稽古法実習」であります。この日は,広島と山口は一つのグループを作って回り稽古を行い,他の県の受講生が講師に掛かっていくことを許されました。金村先生と最初に稽古をお願いし,その後は在津先生,山﨑先生,宮本先生,広田先生,野依先生,大上先生他,たくさんの先生方と稽古をさせていただくことができました。野依先生からは,攻められて思わず手元が上がったところを心にまで響くような小手を頂き,特に印象に残りました。
その後閉講式が行われ,無事に講習会を終了しました。参加された先生方,たいへんお世話になりました。今後ともよろしくお願いします。
(2006/7/9) |
|
 |
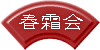 |
|