~お世話になりました~(10月20日)
安易にお引き受けしたものの、果たしてどうなるものやら。こんな場面は自分を試されているのだといつも感じます。次に生じる感情は自分は是だけのものである、これ以上でもなければこれ以下でもない。普段の自分を精一杯演じることだけを心がけよう。そんな心境で臨みました。これこそが剣道で学び得た自分の姿なのだから。
連盟の先生方が参加されたことに愛情を感じ、元気いっぱいの子供たちの姿に何かを感じ取ってもらえたのか一抹の不安はありますが心地よく高速道を北上する帰途につけました。有難うございました。
申し遅れましたが、気持ちよく剣道形が打てました。今度どこからか声が掛かりましたら再度お相手してくださいね。
剣道形稽古 覚え書き(最終回)(10月20日)
・構えを解いた高さは,膝下3~6㎝,何より打太刀の高さに合わせること。
私にとっては,本番でさえ稽古でありました。いや,本番こそが本当の稽古であったのかも知れません。
最後の練習で,わざわざ広島県一の高校生二人がチェックしてくれた,構えを解いた剣先の位置が肝腎の本番で高くなりました。実は,私自身も気付いていたのです。
剣道形の稽古の中でいつも感じたのは,「ここはどうかな」と私が心配したところは,こちらが口に出す前にすかさず指摘していただける心地よさでした。
そして,今回も剣道形が終わって,最初に仰ったことは「あの構えの解き方はちょっと高かったなー」。とてもうれしかったです。
剣道形を打っている最中は,夢中で,この心地よい時間がずっと続いて欲しいと思ったくらいです。
剣先を下げきれなかったのは,下げてしまったときに気を切らないようにする自信がなかったのです。決められた高さではあっても,そこまで下げてしまうと気が切れてしまうのではないか,そんな心の葛藤がありました。しかし,それも今の私の実力です。取り繕った剣道形より,自分の姿をさらけ出した剣道形を受け入れ,今後の糧にしていきたいと考えます。
生徒が書いてくれた感想文と,収録したビデオテープは来週中にお届けできると思います。楽しみにしていてください。
>申し送れましたが、気持ちよく剣道形が打てました。
>今度どこからか声が掛かりましたら再度お相手してくださいね。
私にとっては,最高のねぎらいの言葉です。
でも,ちょっと本気にしてしまいそうな自分が恐いです(^^;)
TO プレジデント範士 様
先生は,すべての剣道を志す者にとってスーパースターです。
今回ご指導いただいたことを宝として,私も剣道を通して少しでも社会の役に立てる人間になりたいと思います。
本当に,ありがとうございました。
~鶴の首~(10月27日)
講演会のビデオと感想文お送りいただき有難うございました。何度も繰り返し自分の姿を確認することができました。自分の形を第三者として見る事ができ勉強になりました。私自身の反省事項も何点か見ることができました。
打ち太刀と仕太刀の関係ではやはり、構えを解いたときの剣先の高さの違いが気になりますね。次に上段のとき(1本目)の立ち姿が雄雄しく颯爽と鶴の抜けた首のような気構えの表現に繋がればいいと思います。
子供の感想文ではほろりとさせられる文面に何度も出会うことができ、平素の先生方のご指導が生きていることに喜びを感じました。29日の大会には所用のため参加できません。欠礼して申し訳ありません。
講演会こぼれ話(10月27日)
この講演会を開催するにあたり,剣道の経験がある本校校長と私はソワソワ,ワクワクしておりましたが,講演の前に他の先生方にもプレジデント範士の素晴らしさを分かって頂く必要がありました。いや,そのことが私の使命であると考えておりました。
よく尋ねられたのは,剣道形をすることになったプレジデント範士と私の力量の差はどれほどなのか,つまりは範士八段と錬士六段の関係でありました。
剣道を全く知らない方にこのことを説明するのは結構難しいところがあります。六段の私に向かって,「あともう少しで八段だね」などと平気で(ご本人は真面目に)言われたりするのであります(^^;)
実際には,次のように説明しました。
(その1)
「例えば名球会の少年野球教室で王選手が野球を教えに来てくれたとします。キャッチボールを説明するのに,大勢取り囲んだ子ども達の中から,『ハイ君,このボールを受けてごらん』と王選手からボール渡され,引きつった笑顔を見せている少年が僕です」
(その2)
「例えば私が剣道のことを深く修行したいと思い立ち,交通費も研修費も自腹で全国レベルの研修会に参加したとします。その時全国から集まったたくさんの研修生たちが,一度だけでも稽古をお願いしたいと並み居る八段講師の中から選ばれるのがプレジデント範士です」
(その3)
「私が中学生の頃から憧れていた先生がプレジデント範士です」
(その4)
「私が名古屋で六段に昇段させていただいたとき,プレジデント範士は審査員として他の会場で審査員をされていました」
いま考えても,やはり今回の剣道形は夢のような出来事でした。
先生のご指導を,しっかりと胸に刻みます。
事務局長,プレジデント範士に問う(10月29日)
高体連新人大会の審判に行ってきました。
今日感じたのは,今も昔も「高校生はスピードが命」ということ。
「攻め」とか「体勢」なんかどこ吹く風とばかりに,「空いた!」と思ったらどんどんと打ち込んでいきます。
こんな時代もあっていいとは思いますが,ずっとこのままでは行き詰まるんですね,これが。
実は,そのことに気付いてからが剣道はおもしろいと思うのです。
高校生たち,その日まで剣道を続けるんだぞ!
今も昔も「高校生はスピードが命」と書いたのにはわけがあります。
いまを遡ること26年前,私は「スピードが命」を否定するような不思議な練習を経験したのです。
当時高校1年生だった私は,プレジデント範士が顧問を務めておられたA芸高校へ部活で出稽古に行きました。
なんとそこで範士の指導のなかに,高校生の常識では理解できない練習法があったのです。
どのような内容だったかというと・・,
まず中段から相手の竹刀をトントントンと踏み込みながら3回払って攻めていく。普通はここから間を置かずにスパンと打つところであるが,その時範士は次のように言われた。
「いいか,ここで相手をよーく見て,一呼吸おいてから打ち込みなさい」
当時高校生の私には???,何のことやら理解できない。
しかし指導者に言われたことなら「どんなことでもとにかくやる」のも高校生である。
その時はこの練習にどのような意味があるのか理解もせず,いや考えもせずと言った方がいいでしょうか,とにかくその練習をくり返しやらされたのでありました。
そしてなんとなんと,このたび26年振りにあの練習の意味を範士に問うたのであります。
「あの練習は何だったのですか」と。
さすがはプレジデント範士であります。
その意味をしっかりと説明してくださいました。
プレジデント範士,答えて曰く,
「あの時一呼吸置かせたのは,正しい姿勢から打ち込ませるためである。高校生はスピードに頼って打ち込むことが多いため,どうしても崩れたままの体勢になりやすい。それで,時々あの時のように正しい体勢から打ち込ませる練習を取り入れていた」と
このときの私は,26年前にいだいた疑問がいままさに解けていく,そんな爽快な気分の中にいました。
ひとしきり感激したあとで,ふと気付いたことがあり,続けて範士に問いました。
「先生,これって高段者向けの稽古法ではないですか?」
プレジデント範士,再び答えて曰く
(どこまでもさらりと)
「うん,そうだよ」
範士は高校生に対しても,遠い将来を見据えた稽古をさせてくれていたのであります。
またまた感激の事務局長,ひと言「参りました」。
恐るべし,プレジデント範士!!
どこまで深い,プレジデント範士!!
~感性こそ成長の源~(11月2日)
指導者として稽古の方法は何がしかの狙いをもって行うものですが、肝心の稽古者のほうがあまりその狙いが理解できていない場合が多いようです。その原因は指導者がしっかりと狙いを伝えていない場合が多いようです。
それにしても練習試合にきたその一日の稽古方法を26年たっても自分の疑問として抱き続けているその感性こそが、素晴らしい事であり、自己の求める姿勢を現しているものなのだなぁと感心の至りでした。当時の状況を思い起こしながら精一杯返答させていただきましたが、今考えても基本の繰り返しを如何に変化をつけながら繰り返していたのだなぁと懐かしくさえ思います。
私にとって剣道とは(11月2日)
26年前,部活の出稽古で訪れたA芸高校の剣道場。一体そこには何人の高校生剣士がいただろうか。
二級上には,今年のインター杯でN田高校を率いて全国準優勝に輝いたN依先生,毎年11月3日に日本武道館で開催される全日本剣道選手権大会に出場されたU本先生,一級上には,広島県警で大将を務められたI岡先生,また同級には昨年の岡山国体において東京都との決定戦の末,広島少年女子チームを第3位入賞に導いたH田先生,いま思い浮かぶだけでもまさにきら星のごときスター選手たちが輝いていた。
私はと言えば,そこに50人の高校生剣士がいたならば,おそらくは48番か49番手,もしかすると50番手の選手であったかも知れない。
そんな私が,曲がりなりにもいま剣道を続けていることは,不思議と言えば不思議である。
ホームグランドの春霜会では,はじめは選手として実績を持った後輩の上座に座ることに居心地の悪さを感じていた。ましてや稽古が終わって挨拶に来られても,一方的にたたかれている自分が何をアドバイスして良いやら,しゃべるのが苦痛でさえあった。
しかし,ある時気付いたのである。
私が上座に座るのは,私が強いからでも偉いからでもなく,大きな剣道という流れの中での一つの役割であるということを。
そのように考えるようになってからは,少しずつではあるが自分は自分でいいんだと思えるようになった。
お互いの剣道を高めていくために,自分の意見が言えるようになった。
剣道も変わったと思う。
良き師に恵まれ,先輩方に引っ張り上げてもらいながら,また後輩達に背中を押してもらいながら,おかげさまで幸せな剣道人生を生かさせていただいております。
今回プレジデント範士にご講演いただいたことは,弱い私がここまで剣道を続けてきた天のご褒美だと思えて仕方ないのです。
(2006/11/2) |
|
 |
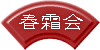 |
|