事務局長,東城高校へ行く(9月22日)
今日は,午後から校長と共に東城高校へ行ってきました。
要件は,東城高校の藤原校長先生に本校生徒への講演をお願いするためです。
「その道から学ぶPartⅤ ~剣道範士 藤原崇郎さん~」
事務局長が勤務する中学校では,「総合的な学習の時間(将来への展望領域)」の一環として,定期的に各界で活躍されている方々をお招きして,ご講演いただいております。
今回は藤原校長先生をお迎えして,これまでの歩みと剣道を修行する中で学んだことや感じたことを語っていただくことになりました。
いやぁー,緊張しました。なにがって,あなた,あの藤原範士に直接お会いして講演をお願い申し上げるわけでありますから,もう,ドキドキであります。以前電話でお願いしたときには一応内諾を頂いておりましたが,それでも決定するまでは心配で心配で,先日の学剣連審判講習会や範士授与記念祝賀会のときにも,「センセー,あのー,例のあの件,よろしくお願いしますね」と消え入りそうな声でお願いし続けてきました。
本校の校長は剣道錬士五段でして,もちろん藤原範士のご活躍はよく存じております。実はそのようなこともあって,今回の講演会の企画がすんなりと認められたのであります。
明日から全日本東西対抗のため新潟へ出発されるというお忙しいなか,藤原先生からは本校生徒のために最大限努力するとの心強いお言葉を頂きました。
ところでこの講演会では,講師の方に必ず実演をしていただき,生徒にその「すごさ」を間近に見せて頂くコーナーがあります。今回も生徒との稽古などいろいろな案があるなか・・・,
本校校長:「では講演のあとの実演の方は,いかがさせていただきましょう?」
藤原範士:「ああ,どんなことでもいいですよ。私ができることであれば何でもしますよ!」
校長:「そうでございますか。では,剣道形などいかがでしょう」
範士:「いいですね。稽古だけでは素人にはわかりにくいところもあるので,剣道形はいいですね」
校長:「それではそのように準備させていただきます」
(事務局長心のつぶやき)
やったー,藤原範士の剣道形がまた見られるで。
(注:藤原範士はこの夏,広島市で開催された全国学校剣道連盟指導者研修会で剣道形の講師を務められています)
ラッキー。役得じゃのー。
ところで校長,剣道形ゆうたら,なんぼー範士がすごいゆうても一人じゃーやってくれてんないで。どうするん?
えっ,ま,まさか・・・
(次週「事務局長危うしの巻」へつづく)
剣道形稽古 覚え書き(その1)(10月3日)
・呼吸を止める(止まるように集中して打つ)
・瞬きをしない(しないように集中して打つ)
・剣先の高さは相手の咽喉部から顔の間。竹刀を構えたときの剣先の高さに比べ高い。
・姿勢は頭のてっぺんを天井に引っ張られるようなイメージで顔を起こし,大きく構える。
・「真剣勝負」の雰囲気で形を打つ。気を抜かないことが剣道に生きる。
・下がるとき「1,2,3,4,5」のあとの「6」を送り込む(引き込む)。
・構えを解いてから後退するところや,七本目が終わり元の位置に戻ってから蹲踞するところなどでは十分な間を置く。
・一本目および残心における上段については,左こぶしをやや前に出し,なおかつやや刀を起こして大きく構える。
・一本目,六本目の残心への移行では,相手の顔面を突き刺すような迫力を出す。
・四本目,3歩前に出たあとの打ちは,相手の頭のやや上の高さになるように低く打つ。刀を徐々に下げるていくときには鎬を削るつもりで,中心方向に圧力をかける。
・五本目,相手の眉間の高さに剣先を自然に下ろして残心につなげていく。
・七本目,元の位置に戻るときは,最後に一歩前に出る感覚で戻る。
剣道形稽古 覚え書き(その2)(10月5日)
・仕太刀「トー」のあと,気を切らないようにして元の位置に戻る。(9歩の間合いに下がるときも同様)
・3本目,打太刀の(水月への)突きを凌ぐときには,手を前に出すようにしながら後退して凌ぐ。
・5本目,擦り上げ面はギリギリのところまで我慢する。すりあげる瞬間は「カン」。
・5本目,擦り上げ面から残心への移行は,「①トー,②オー③オッ」と行う。(①擦り上げ面②剣先を相手の眉間へ③残心)このあと,しっかりとした残心を取り,打太刀の動きに合わせて元の位置へと戻る。
・6本目,擦り上げ小手のタイミングに注意。
・7本目,抜き胴のあと刀を合わせると,仕太刀寄りの位置で交差している。したがって,回りながら元の位置に戻るとき,打太刀はやや後ろへ下がり,仕太刀はやや前へと出る。
剣道形稽古 覚え書き(その3)(10月11日)
・1,2,3,4,5(,6)と元に戻るまで気を切らさない。ここはだいぶできてきた。しかし,次に展開するとき背伸びをするような動作のあと構え直したり,あるいは剣先を必要以上に上げたところから構え直している。「さあ行くぞ!」とか「よし来い!」といった風にも見えるが,それでは,その動作をする直前は本当にそれで良かったのか(切れていなかったのか)。1本目から7本目まで,気を切らせるところはない。
・3本目,下段から上がってくる際には,交差した点がくさびを打ち込んだイメージで。
・3本目,仕太刀が突き返すのは「五分と五分」,次の位詰めは「六分と四分」でなければならない。これで打太刀は「まいった」と感じる。
・4本目,打太刀が右肺を突く「端」を捉えて仕太刀は面に返す。
・6本目,打太刀が左上段から中段に戻り小手,続く仕太刀の擦り上げ小手までをスムーズに行うこと。仕太刀は相手のどのような変化や動きにもどんどん前に出て対応していく気持ちでいること。
自分自身が違和感を持った箇所を逃さず指摘していただく心地よさを感じます。
剣道形稽古 覚え書き(その4)(10月16日)
・構えを解いたときの剣先の高さをそろえる。(横から見てチェックしてもらう)
・二本目,形(かたち)としての残心はないが,小手を打ったあと刀を自然に中心方向へ向ける。その後打太刀の動きがあり,元の位置に戻る。
・三本目,下段から突がくるところは,中段までしっかり構えを上げる。
・四本目,切り結んだ相打ちの高さは頭上5㎝。
・五本目,擦り上げるとき,腕で描く半円の中に手首で作る半円(三日月の形)がある。(ただし刀の場合は鎬を利用できるため,中段に構えた時の角度によっては,腕をそのまま自然に上げていく場合もある)
・六本目,擦り上げ小手は右手の甲を刀にイメージして行う。
稽古する前に,高体連の剣道形大会で優勝した生徒の剣道形を見ました。摺り足の美しさと,残心へ移行するときの切れのよさがたいへん参考になりました。
緊張感と達成感の混沌(10月20日)
「その道から学ぶPartⅤ ~剣道範士 藤原崇郎さん~」
藤原先生に講師をお願いしたとき,果たして本当に来ていただけるかどうか心配しましたが,「うん,い~よ」とこちらが拍子抜けするくらいの快諾をいただきました。先生は今回の講演の中でも,「自分を育ててくれた剣道を通して社会に恩返ししていきたい」と仰いましたが,日頃からそのように考えておられるからこそ気持ちよく引き受けていただけたのだと気付きました。
いま,生徒達に講演いただいたことに感謝すると同時に,来ていただいて本当に良かったと実感しています。この講演会で生徒は現在の自分を振り返り,これからの自分を考えることができました。感想を読んでみると,自分の生き方に迷っていたり,悩みを抱えている子ほど先生のお話が心に届いていることがわかります。
TO mini98さん
剣道形をしっかりと見届けてくださり感謝です。
学ぶことが多すぎて,未だに興奮冷めやりませんが,一生の思い出になりました。このような機会がなければ,範士のお相手を務めさせていただくこともなかったことでしょう。
mini98さんや,剣道を素振りから教えてくださった浅原先生,いつもお世話になっている春霜会会長で来女木剣道スポーツ少年団1期生の伊藤良治先輩に見守られた中で剣道形を披露することができ,本当に幸せでした。
(追伸)
トップページからリンクを貼っている藤原先生の写真(全日本東西対抗副将戦)が,今月号の「剣窓」の表紙を飾っています。
(2006/10/20) |
|
 |
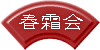 |
|