「さっちゃん,痛いことはないか?」
「うん」
面紐がグイグイと締め上げられ,耳の奥がキーンと鳴った様な気がした。
剣道を始めて間もない小3の私は,自分ひとりでは面を着けることもできず,人の手を借りねばならなかった。
痛くないかと聞かれ,紐の位置によってはひどく痛いのだが,そうとも言えず「うん」と答える他は無かった。
しかしその一方で,引き締まった面紐が体の奥の方ある闘志を掻き立てるのを感じていた。
大きな声で,強く踏み込み,会心の面を打ち込め。
自分が剣道をやってこられたのは,初めからまわりの支えがあってのことだったと,今更ながらに気付く。
指導者になりたての頃,少年剣士を引率して大会に参加した。
その大会には一般の部があった。
大会全体から見れば,おまけの様な存在である。
若い選手との対戦に,一本負けを喫したのであるが,その試合で終始攻め抜けたことに,密かに充実感を覚えていた。
おまえは負けた試合に満足をしたのかと問われれば,確かにそうだとしか答えられない。
自分にしか分からないはずの感覚。
「さっちゃん,よう攻めとったのぉ」
おまけの様な試合でも,しっかりと見てくれる人がいる。
剣道を続けていくことに自信を与えてくれたひと言。
おじちゃん,思いは一緒だったね。
おじちゃんは眠る様な安らかな顔だった。
「おじちゃん,ありがとう」
心で呟くと,涙が止まらなかった。
(2009/4/26) |
|
|
|
|
|
 |
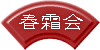 |
|