貴重な「構え」を拝見!! (2007/10/23)
本日mini98さんにお誘いいただき,7時半からH大学剣道部を訪問。
プレジデント範士も剣道部の師範として学生さんを指導しておられました。
稽古では,プレジデント範士が○段の構えに(ほんの少しの間ではありましたが)。
わたくし,初めて拝見しましたので稽古後のmini98さんに
「いっ,いまの範士の構え見た!?」
と興奮しながら聞いたところ,プレジデント範士の○段は見たことがないとのこと。
なんかちょっと得した気分。
とってもレアな体験でありました。
(いやぁ〜,カメラ持っていけばよかったなー)
以上報告おわり。
○段のフジワラ (2007/10/24)
昨年のプレジデント範士講演会では,剣道経験のある校長(Y大剣道部出身)が
「○段のフジワラ」
と何度も言っておりました。
同世代の方々にとっては,範士のあの構えは,強烈な印象なのだと思います。
錆付いた●段 プレジデントもどきF (2007/10/25)
火曜日は遠いところご苦労様でした。
相手の学生が上段の構えだったので私のほうも、少しの時間だけ合い●段に構えてみましたがソレほどまでに感激していただいて有難うございます。そういえば、最近執ることなどほとんどなかったようです。
”火の構え”といわれる●段は燃え盛る気魄で相手の上から”乗る”感覚を体得するには稽古必須のアイテムだと思います。事務局長さんが見えているときに、●段の学生がもし掛かってこなかったらさらに、私に遊び心が生じなかったらおっしゃるとおり見られなかったでしょうね。そう考えると。わざわざ遠方から足を運んで兄弟弟子の精進振りを観察にこられるその真摯な態度に対するご褒美だったのかもしれませんね。
それにしても●と表記する必要はなかったみたいですね。バレバレですよね。
Re.錆付いた●段 (2007/10/25)
プレジデントF 様
構えのこと,少し大げさに書きすぎたと反省しているところです。
もしかすると範士は,「この構えは封印する!!」と(「巨●の星」や「あ●たのジョー」のような雰囲気で)宣言されていて,自分がこんなことを書いて迷惑をかけたのではないかと妄想しつつ(笑)心配しておりました。
前任校の校長もそうですが,地元剣道連盟の方々が昔話をされるのに「範士の●段はすごかったんでぇー」と構えのことが話題に上ることがあります。
年配者ほどその傾向が強いと分析しています(あっ,またまた失礼しました)。
ところでお尋ねしたいことがあります。
先日,mini98くんとの稽古は面返し胴で終了されましたが,数年前の勝浦の研修会ではほとんど返し胴は打っておられなかったように記憶しています。
他の先生方が誘ってからの返し胴を多用されていた中でとても印象に残っているのですが,講習会などで稽古を付けるとき返し胴はあまり打たないようにしているとか,そのあたり何かお考えをお持ちでしょうか。
毎度不躾な質問で申し訳ありません。
道の歩み プレジデントもどきF (2007/10/25)
上段は高校時代に恩師の指導方針で師弟全員必須科目でした。学生時代も両刀を使い分け社会人になっても県内の大会等は8割上段で当分やっていたように記憶していますし、上段のほうが勝率も良かったようです。
30半ばを過ぎたころから(7段合格)は試合も稽古も中段でいくと決めました。その理由は、攻防に最適な中段を少しでも追い求めたい。さらに剣先を通して相手の気力を充分に対の気持ちで受け止める中で動揺しない自分作りができるのではないかと言う狙いをもって。
今現在結果的には一番いい時期に切り替えることが出来たのではないかと思っています。 鋭い視点を聞かせていただいて恐縮していますが返し胴については、手元を浮かさない(気持ちの動揺)ことを心掛けることに執着した時期に返し胴は打たないようにしようと心掛けました。尾張八段戦での船津選手の返し胴を頂戴したからではないのですが、相手の掛かりが見えるとき更には、誘いに乗ってくる時には打ってもいいかなと思いいたしています。
それにしても、先人の求めている心に思いをいたすことが出来るその”観の目”に敬服の至りです。
貴重なお話をありがとうございます (2007/10/25)
お返事ありがとうございます。
何かものすごく大変なことを聞いてしまったのではないかと,いま動揺しています(笑)
H大学でのことを「遊び心」と書かれましたが,その言葉の中にこそ強さの秘密が隠されているのではないかと睨んで(笑)おります。
先日本校にゲストティーチャーとしてお越し頂いた「職業人講話」では,職業としての「体育教師」を語っていただきましたが,球技の授業で生徒に審判を任せ,自分も一緒になってゲームを楽しんだといったお話に繋がっているなーと感じました。
余裕から生じる「遊び心」が人間性に広がりを持たせ,剣道に生かされているのではないでしょうか。
|
|
 |
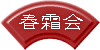 |
|