剣道を教えることは,剣道人としての成長につながる。技能の面で子どもたちとの稽古の中で力を付けることは可能であり,何より教えるということ自体精神の修養であると考えます。全剣連の社会体育指導員養成講習会の申込用紙に,指導歴を書く欄があり自分がどのように指導してきたのか改めて振り返ってみました。
私が少年剣道に携わったのは就職してすぐ,来女木剣道スポーツ少年団の指導者のひとりとして,また中学校の部活動の指導者としてでした。スポ少指導の方は,私自身の師でもある浅原晃先生,春霜会第1期生の伊藤良治先生,4期生の岩崎猛先生が既におられ,そこに7期生の児玉晃先生と一緒に加わりました。スポ少の設立当初から来女木剣道スポーツ少年団保護者後援会が強力なバックアップ体制を敷き,活動はたいへん活気のあるものでした。そのとき私が感じたことは,社会体育では指導者と後援会とは車の両輪であり,親の情熱はストレートに子どもたちに伝わっていくということでした。ときどき「子どもがいやがるので,試合は観に行かない。」と言う保護者がいますが,私はそんなことはない,むしろその逆だと思います。指導で難しいのは,子どもたちに剣道の楽しさを感じさせ,剣道を続けさせていくということです。小学校6年生まで育てた子が,中学で剣道を続けないときは,やはりがっくりきますね。子どもが楽しいと感じるのは,成就感や達成感を持ったときだと考えられますが,試合に勝たせることも大きな要素です。正しい剣道(将来に繋がる剣道)を指導しながら勝っていくことも大事なことだとつくずく思います。
一方,中学校の部活動は全員加入が原則であり,様々な子がいますので社会体育とは違う面があります。部活動の良いところは,日々練習ができることで,忙しい毎日の中では自分の稽古もここが中心となります。実際,四段を受けに行く前は一般との稽古はほとんどできませんでしたが,攻めて出端をとらえる稽古を繰り返すことで,稽古不足を補いました。当時の子どもたちが,自分を四段に合格させてくれたと思っています。
(2000/6/10) |
|
 |
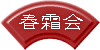 |
|