48・X線の放出だけで輝かない天体とは
<X線天体の正体>
X線天体の正体は何だろう。
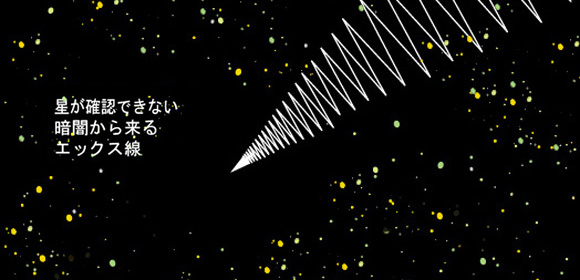
恒星はその光質を調べてランク分けされています。
T型(表面温度1300度以下)準褐色矮星
L型(1300〜2500度)褐色矮星
M型(2500〜3900度)赤色星アンタレス、ベテルギウス
K型(3900〜5300度)アルデバラン、アークツルス
G型(5300〜6000度)太陽
F型(6000〜7500度)カノープス、プロキオン
A型(7500〜10000度)シリウス、ベガ
B型(10000〜29000度)リゲル、スピカ
O型(29000〜52000度)シグマ、天の川銀河で2万個あまりといわれています。
青白く光り連星や偏光でも知られる1等級のスピカが2万度ですから5万度はさしずめエータ・カリーナあたりか?最近発見された最も迫力のある星は LBV 1806-20 で光度がただいまNo1で 太陽光度の4000万倍、太陽径の150倍で太陽質量の120倍だそうです。
いずれにしても表面温度で5万度を大きく超える恒星は未だ見つからないということです。
太陽など輝く恒星の光など電磁波はすべからく原子核を周回する電子から発せられると考えられます。電子が定員未満のイオンであっても可能でありそれらは表面を覆う粒状班に存在しているでしょう。ですが原子核を離れた自由電子に電磁波の生成能力はないと思われます。
理由は、太陽の周囲を取り巻いているコロナは自由電子の集まりですが100万度の高温になっても電磁波情報を出していません。また太陽の表面は4000度あるいは6000度といわれており、ここでは電子が原子核を周回する原子や一部の分子が存在できる温度だといわれています。
さらに太陽光のスペクトルは多くの元素から発せられている光が合わさっていることを示す幅広い虹色になっています。このことで光源である太陽表面には鉄など多くの元素が混ざり合って存在しておりそれら元素の電子が発光していることがわかります。
これらのことで輝く恒星の表面はすべからく(抱える電子の数がゼロとなる)完全電離温度以下であることが想像されます。
≪太陽の光源は中心の核融合で生じ、多くの年月を経て表面に移動してくる、とする説があります。中心で生じるのはガンマ線のみとしており、年月を経て光に変わるとしますが、電離元素ほかで満たされた太陽の中で同一のガンマ線は数秒さえも生きて留まってはいないでしょう。仮りに5秒間生きて留まるなら、夜の部屋の明かりを消しても5秒間は明るいはず。 この説は疑問に思います≫
標準的恒星である太陽は中心部が1500万度で表面が6000度、周辺部のコロナが100万度と言われています。更に高温な恒星でその表面温度が5万度を超える場合はどうなるのでしょうか…
電子を一つ有する水素の電離温度は1万度といいます、宇宙に多量に存在する鉄は26の電子を有しますが、5万度あたりで26すべて電離してしまうのではないでしょうか。
鉄やニッケルなどを完全電離させればそれよりも重い重元素は量的に微々たるもの、或いはそれさえも完全電離となってしまうのではないでしょうか。
その5万度を越えてしまったため恒星は輝きを失ってしまったのでは…
輝くための粒状班を作ることが出来ないのでは…
時を経て表面温度が下がると再び忽然と出現するのでは…
あるいは、以前は輝いていたのだが熱が蓄積され輝くことが出来なくなったのだろうか、もしそうであれば核融合反応が加速していることになり超新星爆発の前触れなのかも知れない!
この表面が高温に過ぎる星は結構数多く存在するのではないでしょうか。
高温であるとは構成物質に重元素が多いということで引力も強いということですから、多くの隕石を引き寄せ高温の大気との摩擦で蒸発し、周囲を微細な金属元素が厚く取り巻き、コロナの自由電子と衝突して多量のX線が発生するでしょう。
また中心部の核融合で発生するガンマ線は内部物質に衝突反射しエネルギーを弱め一部がX線に変わり瞬時に恒星の表面に達して宇宙に放出されるでしょう。それらは恒星の温度が急激に加算されるのを防ぐことにもなっているのでしょう。
もし輝く恒星であればガンマ線やX線は表面を覆っている粒状班の電子に吸収されてしまいますが粒状班はありません、そのため輝く恒星よりも格段に多量の放出となります。よってコロナの自由電子は数千万度の超高温になっているかもしれません。(これくらいの高温であれば自由電子さえもX線を発生させるとの説もあります)
光源のない場所から届くX線の観測はこの「輝かない恒星」を観測しているのではないでしょうか。
記
白鳥座のX1はそのうち輝くかも知れない…あるいは超新星爆発するかも知れない…
2012.6.28
48→→
HPへ
→→
スマホへ